2022年03月21日
3/21 今季最後の活動
大分エコクラブにとって、今季最後の伐採活動となりました。(4月以降の伐採木は、虫が入る為に活動は行いません)
今日も1現場1作業班を徹底しながら、滑車とウィンチを使っての伐採となりました。
ロープは滑車で角度を振ります。
また、滑車の使い方もみんなで共有しながら進めます。
また、時にはスローラインを複数使ってロープをかけやすくします。

昼休みには、広場に集まって、「チェーンソーを使い納めする際のメンテナンス」具体的には、燃料タンクの清掃、フィルターの清掃。オイルフィルターの清掃。などを行いました。


午後は、伐倒した大木を坂下から運び上げるのに、電動ウィンチやダブル滑車などを使って運び上げを行いました。
今日も1現場1作業班を徹底しながら、滑車とウィンチを使っての伐採となりました。
ロープは滑車で角度を振ります。
また、滑車の使い方もみんなで共有しながら進めます。
また、時にはスローラインを複数使ってロープをかけやすくします。
昼休みには、広場に集まって、「チェーンソーを使い納めする際のメンテナンス」具体的には、燃料タンクの清掃、フィルターの清掃。オイルフィルターの清掃。などを行いました。
午後は、伐倒した大木を坂下から運び上げるのに、電動ウィンチやダブル滑車などを使って運び上げを行いました。
Posted by 大分エコクラブ at
10:07
│Comments(0)
2020年04月06日
不要になったクヌギの大木をカット
晴天となって6〜7名のメンバーが集まり、公園整備の際に不要となったクヌギの大木を分けてもらいこの日小さくカットして、万バーが各自持ち帰るようにしました。
打ち合わせを行い人数分の山を作り、等分に分けた方が良いと言うことになりそれに従って作業をすすめました。
1時間もすると6〜7つのカットした薪の山ができてこれを斧で割って持ち帰るように作業を進めます。コロナウィルスの関係からお互いの距離を保ち

作業は午後2時にはすべてをカットして、現場を清掃してカットしたクヌギを早々に持ち帰りました。

その模様です。
打ち合わせを行い人数分の山を作り、等分に分けた方が良いと言うことになりそれに従って作業をすすめました。
1時間もすると6〜7つのカットした薪の山ができてこれを斧で割って持ち帰るように作業を進めます。コロナウィルスの関係からお互いの距離を保ち
作業は午後2時にはすべてをカットして、現場を清掃してカットしたクヌギを早々に持ち帰りました。
その模様です。
Posted by 大分エコクラブ at
18:19
│Comments(0)
2019年04月21日
チェーンソーメンテナンス勉強会」
平成30年度の総会を大分市において今日21日に行いました。

総会終了後。毎年不定期に行っているチェーンソーのメンテナンス勉強会を今年は本格的にやってみる事にしました。
今回は、メンバーのoさんがコンプレッサーを持参してくれたので、これを使ってホコリを軽快に吹き飛ばします。

メンテナンスの順番は、チェーンソーの刃を取り外してバーの部分に付いたバリを取ったり、エアーフィルター、回転部分のホコリやオイルをスプレーで洗い流して、1つ1つ綺麗にして行きます。


次に、チェーンオイルのタンク。混合油のタンクからすべての燃料を出して、中をガソリンやパーツスプレーで洗い流して、フィルターにつまったホコリもスプレーで綺麗にします。



こうして、参加者すべてのチェーンソーは、綺麗に見違える様になりました。

総会終了後。毎年不定期に行っているチェーンソーのメンテナンス勉強会を今年は本格的にやってみる事にしました。
今回は、メンバーのoさんがコンプレッサーを持参してくれたので、これを使ってホコリを軽快に吹き飛ばします。
メンテナンスの順番は、チェーンソーの刃を取り外してバーの部分に付いたバリを取ったり、エアーフィルター、回転部分のホコリやオイルをスプレーで洗い流して、1つ1つ綺麗にして行きます。
次に、チェーンオイルのタンク。混合油のタンクからすべての燃料を出して、中をガソリンやパーツスプレーで洗い流して、フィルターにつまったホコリもスプレーで綺麗にします。
こうして、参加者すべてのチェーンソーは、綺麗に見違える様になりました。
Posted by 大分エコクラブ at
18:11
│Comments(0)
2019年01月20日
クヌギの伐採とチェーンソー勉強会
今日1月20日は、2ヶ月前に伐採していたクヌギの丸太切り作業になります。作業開始前にあたってチェーンソーの扱い方の基本を教本本を参考にしながら復習します。大分エコクラブの開院は、5〜6年やっている人もいれば、先月入った人もいますからこうして時折チェーンソーの扱いの基本をやる必要が出てきます。

チェーンソーも最近はフルオートのチェーンソーが多くなり細かな調整が必要なくなりましたが、木を切る作業や刃の研ぎ方は自動でやってくれるわけではありませんから常に勉強が必要になります。

現場は、2ヶ月前に伐採したクヌギの丸太を処理作業します。

昼食時にはチェーンソーのメンテナンスについての勉強会です。フィルターの点検。ガイドバーやオイルフィルターの転換。刃の研ぎ方など多くの項目にわたって勉強会を行います。

おかげで、森は見違えるように整備されて明るくなってきました。

今回伐採したクヌギは薪用とシイタケの駒木用にわけて整備します。

3時過ぎにはほぼ今回の作業は終了し、車に積んで持ち帰りました。
チェーンソーも最近はフルオートのチェーンソーが多くなり細かな調整が必要なくなりましたが、木を切る作業や刃の研ぎ方は自動でやってくれるわけではありませんから常に勉強が必要になります。
現場は、2ヶ月前に伐採したクヌギの丸太を処理作業します。
昼食時にはチェーンソーのメンテナンスについての勉強会です。フィルターの点検。ガイドバーやオイルフィルターの転換。刃の研ぎ方など多くの項目にわたって勉強会を行います。
おかげで、森は見違えるように整備されて明るくなってきました。
今回伐採したクヌギは薪用とシイタケの駒木用にわけて整備します。
3時過ぎにはほぼ今回の作業は終了し、車に積んで持ち帰りました。
Posted by 大分エコクラブ at
19:14
│Comments(0)
2016年11月14日
チェーンソーの勉強会
11月13日は、大分エコクラブで夏の「刈り払い機の講習会」に次いで、この冬に目指しての勉強会です。
会場近くには、前日から幾つかの看板を設置して、初参加の人にも分かるようにしています。


会場は、由布市の小狭間竹の山林で、3年前より多くのメンバーが参加して切り開いた森であり広場でもあります。この広場と木材を使って実際にチェーンソーを使いながらその使い方や、メンテナンスの技術を高めて行こうというものです。

今回は初回参加の方には、チェーンソーの刃の研ぎ方を教えてあげる一方で、経験者の方には
1,バラしたチェーンソーから組み立て、起動までの時間を計る。






2,設定した長さにチェーンソーで切り落とす。




3,丸太を上の下から合わせ切り。

この3つのテーマをやってみることにしました。やってみて分かるのは、チェーンソーの刃は良く研げていても、刃の両側の研ぎがしっかり揃っていないと、どちらかに歪んでしまったり、真っ直ぐに切り落とせないという結果でした。

昼食は、みんなで「猪鍋」を思いっきり食べて、

午後は、実際の傾斜地に出て「玉切り」の練習をしたり、傾斜した樹木をメンバーが受け口切りするのを見学したりして、無事に終わりました



会場近くには、前日から幾つかの看板を設置して、初参加の人にも分かるようにしています。


会場は、由布市の小狭間竹の山林で、3年前より多くのメンバーが参加して切り開いた森であり広場でもあります。この広場と木材を使って実際にチェーンソーを使いながらその使い方や、メンテナンスの技術を高めて行こうというものです。

今回は初回参加の方には、チェーンソーの刃の研ぎ方を教えてあげる一方で、経験者の方には
1,バラしたチェーンソーから組み立て、起動までの時間を計る。






2,設定した長さにチェーンソーで切り落とす。




3,丸太を上の下から合わせ切り。

この3つのテーマをやってみることにしました。やってみて分かるのは、チェーンソーの刃は良く研げていても、刃の両側の研ぎがしっかり揃っていないと、どちらかに歪んでしまったり、真っ直ぐに切り落とせないという結果でした。

昼食は、みんなで「猪鍋」を思いっきり食べて、

午後は、実際の傾斜地に出て「玉切り」の練習をしたり、傾斜した樹木をメンバーが受け口切りするのを見学したりして、無事に終わりました



Posted by 大分エコクラブ at
18:28
│Comments(0)
2016年11月14日
チェンソーの勉強会
11月12日に大分メリー商会寄ってみると、恒例の「スチールの日」が開催されていました。

この店に来る方は、市内で園芸や農業をされている方や、趣味で薪ストーブやしいたけを栽培している方が中心のようです。今回は薪ストーブの薪をカットするための台や

安全用品がほぼ一式並べられています。

会場奥では、電動とエンジン式の「薪割り機」が展示、運転されています。

エンジンの薪割り機で、大きな丸太もバリバリと割ってゆきます。

こちらが、電動の薪割り機です。


この店に来る方は、市内で園芸や農業をされている方や、趣味で薪ストーブやしいたけを栽培している方が中心のようです。今回は薪ストーブの薪をカットするための台や

安全用品がほぼ一式並べられています。

会場奥では、電動とエンジン式の「薪割り機」が展示、運転されています。

エンジンの薪割り機で、大きな丸太もバリバリと割ってゆきます。

こちらが、電動の薪割り機です。

Posted by 大分エコクラブ at
09:52
│Comments(0)
2015年12月27日
傾斜地での伐採-3
傾斜地での伐採は、今日で3回目になります。1回、2回とかなりのハイペースで作業をやりましたので、メンバー間で話し合いを行って、

道具置き場を一定の場所に定めて、タバコを飲む方も燃料等から離れた場所で吸うように決めました。

作業は、2班に分けて上が作業をするときには、下の班は離れて見守り、上の伐採が終わったら、倒れた木の枝の処理を下で行う。という風に片方のみの作業をようにしました。




上の班はその後、伐採木の根本を改めて地面近くから伐採して、萌芽が出にくいようにしました。この作業の際にも、伐採した太い木が転げ落ちるために常に下と呼び笛で合図しながら作業を進めます。幾つかの根元は残しておき、反対側の木をチルホールがけするときにこれにワイヤーや、スリングベルトを掛ける為に使います。


午後は、残りの傾斜した木をロープを使いながら目的の場所に切り倒します。

こうして伐採した雑木は、今回も参加人数で平等に振り分けられて、くじで一人一人が自分の割当の木を持ち帰りました。

年明けは、1月10、11日の作業開始になります。良いお年を

道具置き場を一定の場所に定めて、タバコを飲む方も燃料等から離れた場所で吸うように決めました。

作業は、2班に分けて上が作業をするときには、下の班は離れて見守り、上の伐採が終わったら、倒れた木の枝の処理を下で行う。という風に片方のみの作業をようにしました。




上の班はその後、伐採木の根本を改めて地面近くから伐採して、萌芽が出にくいようにしました。この作業の際にも、伐採した太い木が転げ落ちるために常に下と呼び笛で合図しながら作業を進めます。幾つかの根元は残しておき、反対側の木をチルホールがけするときにこれにワイヤーや、スリングベルトを掛ける為に使います。


午後は、残りの傾斜した木をロープを使いながら目的の場所に切り倒します。

こうして伐採した雑木は、今回も参加人数で平等に振り分けられて、くじで一人一人が自分の割当の木を持ち帰りました。

年明けは、1月10、11日の作業開始になります。良いお年を
Posted by 大分エコクラブ at
20:06
│Comments(0)
2015年12月06日
傾斜地でのチェーンソー講習会
12月6日は、チェーンソー講習会を豊後大野市のリバーパーク犬飼で行いました。今回は特に「クライミングの技術」を使って、傾斜した地形を使って1つ1つの用具や使い方を説明しながらの講座です。参加は、県内からチェーンソーを使って伐採作業をやっている方々が、新聞等を見て参加下さいました。

指導は、傾斜地や崖を登ることを得意としているクライマーで臼杵市のFさんとTさんが指導に当たってくれました。

大分エコクラブでも、事前に揃えた用具を使って講師の助言でやってみます。

1度ではなかなか理解できるものではありませんが、回を重ねれば多くのメンバーが理解して作業が出来るようななるでしょう。

昼食時には、テーブルを囲みながら理解できなかったところを質問したりして、大まかな用具の使い方が見えてきたような気がしています。

そして、後半は、自分のチェーンソーを使ってあらかじめ用意しておいた丸太を切りながら、問題点を話ながら技術の向上を目指します。








今日参加したメンバーです。

いよいよ来週から、現場に入ります。

指導は、傾斜地や崖を登ることを得意としているクライマーで臼杵市のFさんとTさんが指導に当たってくれました。

大分エコクラブでも、事前に揃えた用具を使って講師の助言でやってみます。

1度ではなかなか理解できるものではありませんが、回を重ねれば多くのメンバーが理解して作業が出来るようななるでしょう。

昼食時には、テーブルを囲みながら理解できなかったところを質問したりして、大まかな用具の使い方が見えてきたような気がしています。

そして、後半は、自分のチェーンソーを使ってあらかじめ用意しておいた丸太を切りながら、問題点を話ながら技術の向上を目指します。








今日参加したメンバーです。

いよいよ来週から、現場に入ります。
Posted by 大分エコクラブ at
18:21
│Comments(0)
2015年10月18日
発動機の展示会
18日の日曜日に大分市戸次の空地に於いて、昔懐かし発動機の展示会があると知って、出掛けてみました。

聞いてみると、発動機は昭和二十年代あたりから始まって、20年ほど使われていたそうです。私も熊本の実家が農家でしたので、この頃になると村々をこの発動機を使った脱穀機が回っていました。子供の頃はまだ機械らしいものは見たことがなかったので、この発動機の動きや、オイルタンクから「ポタポタ」とオイルが落ちていく様子を見ていた記憶があります。
やっている方に聞いてみると、みなさん職業は様々で自分で農家などの倉から探しだして、自分たちでこうして研究会を持って直したり、自慢したりしているそうです。

女性には理解し難いことかもしれませんが、こうして3〜4人が集まって動かない発動機を懸命に動くように試みている姿は、私達の活動とも何所か通じるところがあるなーと思いました。
この会は、県下で幾つか行われている様で、この戸次では春夏2回あっているとのことでした。
Posted by 大分エコクラブ at
21:14
│Comments(0)
2015年08月04日
チェーンソーをしばらく使わない時の保管方法
7月の中旬にもなると、さすがにチェーンソー使うのも暑くなりますし、蚊や蜂が出てきて山里には入りたくないものですね。
チェーンソーをこの秋までしばらく使わないことを前提にした場合、チェンソーや混合油、チェーンソーオイルの保管をどうするかが大事になってきます。

昨年は、6月に朴木小学校の校庭にて、チェーンソーのメンテナンス講習会を行いましたが、今年度は、由布市の庄内町において勉強会を行いたいと思います。

期日は、8月9日の午前9時〜お昼あたりまでを計画しています。参加を希望される方は、自分がお持ちのチェーンソーと道具類を持ってお集まり下さい。
場所は、https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z-XRdcZvlPMo.kkz0jxYEucG4&usp=sharing
になります。

参加希望者は右の欄の「メッセージを送る」からメールを下さい。
チェーンソーをこの秋までしばらく使わないことを前提にした場合、チェンソーや混合油、チェーンソーオイルの保管をどうするかが大事になってきます。

昨年は、6月に朴木小学校の校庭にて、チェーンソーのメンテナンス講習会を行いましたが、今年度は、由布市の庄内町において勉強会を行いたいと思います。

期日は、8月9日の午前9時〜お昼あたりまでを計画しています。参加を希望される方は、自分がお持ちのチェーンソーと道具類を持ってお集まり下さい。
場所は、https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z-XRdcZvlPMo.kkz0jxYEucG4&usp=sharing
になります。

参加希望者は右の欄の「メッセージを送る」からメールを下さい。
Posted by 大分エコクラブ at
11:40
│Comments(0)
2015年05月22日
イベントの用意
チェンソー体験会を2日後にひかえた22日、メンバー4名で会場のセッティングをしました。

朴の木小学校のグランドを「駐車場」「チェンソー体験コーナー」「薪割りコーナー」「メンテナンスコーナー」などにロープを張って区切りを入れ会場に来た人がすぐに分かるようにしてみました。

特にチェンソーなどを使うところは、ある程度距離をおいて見たり、体験できたりするようにしています。

また、会場は道路からすこし入ったところにあるので、道路を来た人にもすぐ分かるように看板をたてています。

当日は天気が良いとよいのですが。

朴の木小学校のグランドを「駐車場」「チェンソー体験コーナー」「薪割りコーナー」「メンテナンスコーナー」などにロープを張って区切りを入れ会場に来た人がすぐに分かるようにしてみました。

特にチェンソーなどを使うところは、ある程度距離をおいて見たり、体験できたりするようにしています。

また、会場は道路からすこし入ったところにあるので、道路を来た人にもすぐ分かるように看板をたてています。

当日は天気が良いとよいのですが。
Posted by 大分エコクラブ at
18:44
│Comments(0)
2015年05月12日
チェンソー体験会を開催します。
平成27年度の始めにあたり大分エコクラブでは、会員または一般の方で、チェンソーに興味のある方を対象にしてチェンソーに関する体験会を行います。
自分の道具をお持ち頂いても構いませんし、こちらで用意した物をお使い頂くことも出来ます。
チェンソーに関する道具類は、ホームセンターで購入しただけでは刃の研ぎ方や、混合油の作り方、チェンソーの保管の仕方などは、実際にやってみないと分からないことばかりですし、1歩間違うと危険なことが多い機材です。
大分エコクラブは3年前に設立して、多くの専門家の指導を受けて様々な機材を扱えるようになってきました。現在も2〜3カ所の雑木林を伐採しています。
4年目を迎えるにあたって、県内で一人でチェンソーを使っている方々や、これから使おうと思っている方に、少しでもチェンソーの扱い方がより理解できるようになって頂ければと思っています。
参加希望者は、画面右の「メッセージを送る」から「お名前、メールアドレス」を入れて送って下さい。直接来られても結構です。
期日 平成27年5月24日(日曜日)
場所 由布市朴木小学校グランドにて
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zCFEZ-7-mmt8.k_4jHWV2poKg
時間 午前10時~午後3時 (昼食は各自で用意)
内容 1,チェンソー、斧、安全用品、刃を研ぐヤスリの展示。
2,チェンソーの伐採体験。
3,斧を使って薪割り体験。(割った薪は差し上げます。)
4,チェンソーの刃のメンテナンス(点検方法、刃の研ぎ方、しまい方)
5,チェンソーの混合油の作り方。
6、チルホールを使った伐採方法
7、運搬車の運転、操作

朴木小学校

昨年の朴木小学校にて
1,チェンソー、斧、安全用品、刃を研ぐヤスリの展示。

2,チェンソーの伐採体験。

3,斧を使って薪割り体験。割った薪は持ち帰れます。

4,チェンソーの刃のメンテナンス(点検方法、刃の研ぎ方、しまい方)

5,チェンソーの混合油の作り方。

6、チルホールを使った伐採方法

7,運搬車の操作

自分の道具をお持ち頂いても構いませんし、こちらで用意した物をお使い頂くことも出来ます。
チェンソーに関する道具類は、ホームセンターで購入しただけでは刃の研ぎ方や、混合油の作り方、チェンソーの保管の仕方などは、実際にやってみないと分からないことばかりですし、1歩間違うと危険なことが多い機材です。
大分エコクラブは3年前に設立して、多くの専門家の指導を受けて様々な機材を扱えるようになってきました。現在も2〜3カ所の雑木林を伐採しています。
4年目を迎えるにあたって、県内で一人でチェンソーを使っている方々や、これから使おうと思っている方に、少しでもチェンソーの扱い方がより理解できるようになって頂ければと思っています。
参加希望者は、画面右の「メッセージを送る」から「お名前、メールアドレス」を入れて送って下さい。直接来られても結構です。
期日 平成27年5月24日(日曜日)
場所 由布市朴木小学校グランドにて
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zCFEZ-7-mmt8.k_4jHWV2poKg
時間 午前10時~午後3時 (昼食は各自で用意)
内容 1,チェンソー、斧、安全用品、刃を研ぐヤスリの展示。
2,チェンソーの伐採体験。
3,斧を使って薪割り体験。(割った薪は差し上げます。)
4,チェンソーの刃のメンテナンス(点検方法、刃の研ぎ方、しまい方)
5,チェンソーの混合油の作り方。
6、チルホールを使った伐採方法
7、運搬車の運転、操作

朴木小学校

昨年の朴木小学校にて
1,チェンソー、斧、安全用品、刃を研ぐヤスリの展示。

2,チェンソーの伐採体験。

3,斧を使って薪割り体験。割った薪は持ち帰れます。

4,チェンソーの刃のメンテナンス(点検方法、刃の研ぎ方、しまい方)

5,チェンソーの混合油の作り方。

6、チルホールを使った伐採方法

7,運搬車の操作

Posted by 大分エコクラブ at
09:36
│Comments(0)
2015年01月19日
燃料タンク
昨年末より、チェンソー燃料、オイルは、現場で使用する分においては、大分エコクラブで負担することとし、この2つのカンにて好きな方を自分のチェンソーに入れてもらっています。どちらも50:1の混合比です。

現在の山で使っている用具は、メンバーが3〜4人いれば、この滑車と麻ロープを使っての牽引伐採です。上方でツルが絡んでいなければ大体上手く伐採できていると思います。

伐採風景です。
滑車とロープ


現在の山で使っている用具は、メンバーが3〜4人いれば、この滑車と麻ロープを使っての牽引伐採です。上方でツルが絡んでいなければ大体上手く伐採できていると思います。

伐採風景です。
滑車とロープ

Posted by 大分エコクラブ at
12:32
│Comments(0)
2014年06月24日
チェーンオイルをきれいにする。
チェンソーをしばらく使わない場合に、気になるのがチェーンオイル。
そこで、如何にしたら手がべとつかずに不純物を取り除けるかを考えてみました。1〜2Lのペットボトルの容器を使ってやってみました。上の細くなった部分だけを切り取ります。

これを「じょうご」にします。

この部分に、コーヒーのフィルターを差し込みます。

こんな感じです。

残った部分に、差し込めば漉したものが下に確実に貯まります。時間が必要ですから半日がかりでやるようにしましょう。


なお、チェンソーからオイルを抜く際に油がこぼれやすいですから、やや高いところに設置してオイルの口を下に向けておけば安心です。

この後、チェンソーの中のオイルを出し切ったら、中をガソリンかパーツスプレーで綺麗に洗ったり、歯ブラシで隅々をきれいにして、冬まで保管です。
そこで、如何にしたら手がべとつかずに不純物を取り除けるかを考えてみました。1〜2Lのペットボトルの容器を使ってやってみました。上の細くなった部分だけを切り取ります。

これを「じょうご」にします。

この部分に、コーヒーのフィルターを差し込みます。

こんな感じです。

残った部分に、差し込めば漉したものが下に確実に貯まります。時間が必要ですから半日がかりでやるようにしましょう。


なお、チェンソーからオイルを抜く際に油がこぼれやすいですから、やや高いところに設置してオイルの口を下に向けておけば安心です。

この後、チェンソーの中のオイルを出し切ったら、中をガソリンかパーツスプレーで綺麗に洗ったり、歯ブラシで隅々をきれいにして、冬まで保管です。
Posted by 大分エコクラブ at
12:02
│Comments(0)
2014年06月16日
チェンソー・メンテナンス勉強会の内容
大分エコクラブが、朴木地区で行ったチェンソーのメンテナンス勉強会の内容です。入会していても初めての参加の方や、朴木地区からの飛び入りの参加者なども含めてまずはお互いの紹介をしました。

これが今回各自が持ち込んだチェンソーです。ハスクバーナ、スチール、新ダイワ等で、排気量も35c〜45cまでまちまちです。

今回まず最初にやったのは、「チェンソーのエンジンを掛ける」です。単純なことですが、かけ方も人それぞれでお互いが見ることで、危ない点、故障につながる点、等が発見できるものです。そして、起動に当たっては、
1,周りを見る(燃料から3mは離れること)子供、人を確認
2,燃料、チェンソーオイル確認。
3,ネジを確認(バーを留めるネジが緩んでいる場合があります)
4,チョーク確認。
5,スイッチ確認。
そして、起動です。今回はこの起動の際にスターターロープを引く方向が真っ直ぐでなかった方もありましたので(摩擦で切れてしまいます)




全ての参加者に自分のチェンソーを起動させてもらって、用意した丸太を3cm幅でカットする、姿勢、エンジン音、カットの仕方などを確認します。


ここで、メンバーで確認できたことは、チェンソーに爪が付いているものは、この爪を使ってカットするとより楽に出来るという意見が出ていました。
こんな感じでしょうか。
この作業を、お互いに見ながらする事で、不断は気付かない事も気付かされる点も多かったように思います。「チェンソーの起動、カット」はこれで終了し、次は、先ほどカットした切りくずを見ながら、切れないチェンソーはどこが良くないのか、「つまりチェンソーの刃に問題がある」場合がほとんどですから、今度は「チェンソーの刃を研ぐ」勉強を開始です。
これまでにチェンソーの刃研ぎ勉強会は、何度かやっていますから、そのたび事にお互いの良いものを取り入れて、道具や研ぎ方はますます進化しています。





これはスチールの刃を研ぐ際に、チェンソーの刃に乗せるガイド部品で、正確に簡単に角度を決められると言うことで評判になっていました。

皆さん真剣にやっています。

午前中10時から始めた勉強会は、またたく間に12時を過ぎて、昼食になりました。食事はこの小学校跡を利用して林田夫婦がオーガニックレストランを始めたと言うことで、皆さんここで食事をすることになりました。

午後は、「この季節になってほぼチェンソーを使い終えたと想定して、チェンソーの仕舞い方、保管の仕方」を勉強です。
1,チェンソーのガイドバーと刃を外して、ガイドバーの清掃をします。
この動画は、長い間ガイドバーをあたっていない方がいましたので、これを平やスリで丁寧に左右に出来たバリを取り払っています。このほか、先端の回転する箇所には、グリース。 溝は細いものでゴミを丁寧に取り払っておきます。根元のオイル口の清掃も大事です。





次は、空気を取り入れる「エアーフィルター」の清掃です。この日は、パーツスプレーを使って清掃できるものは、これで細かいゴミを吹き飛ばしてきれいにしました、一部のフィルターではこれが出来ないものもありますので、この場合にはエアーでする場合もあります。
最後の残ったのは、燃料タンクとチェンーオイルタンクの清掃です。下の写真がオイルをすべてタンクから出しているところで、

紙コップに入れてみると中にゴミが入いっているのがわかります。これをコーヒの濾過紙にかければ元通りにきれいな油になります。

写真ではありませんが、この後すべて出しきったタンクから、オイルフィルターを取り出して(取り出せないものも機種によってはあります)灯油やガソリンで綺麗に洗ったり、パーツスプレーでゴミを吹き飛ばします。また、タンク内に残ったオイルもタンクを逆さまにしてパーツスプレーで洗い流して終了です。
次は、燃料タンクです。ここにもフィルターが中に入っていて、これを取り出してゴムから外して、ガソリンやパーツスプレーで清掃します。また、タンク内もオイルタンクと同様に清掃して終了です。
この後、最後に残った最も大事な作業があります。それは、タンクとエンジンのホースに残っている燃料を使いきって仕舞わないと、この燃料が風化してキャブレターが傷んでしまいます。
通常通りにエンジンを掛けて、止まるまでそのままにしておき、止まったらこれで秋まで乾燥した、日当たりの少ない場所に保管します。
皆さんお疲れ様でした。研ぎ澄まされたチェンソーを持ってまた秋に集まりましょう。

動画は、ここをクリック

これが今回各自が持ち込んだチェンソーです。ハスクバーナ、スチール、新ダイワ等で、排気量も35c〜45cまでまちまちです。

今回まず最初にやったのは、「チェンソーのエンジンを掛ける」です。単純なことですが、かけ方も人それぞれでお互いが見ることで、危ない点、故障につながる点、等が発見できるものです。そして、起動に当たっては、
1,周りを見る(燃料から3mは離れること)子供、人を確認
2,燃料、チェンソーオイル確認。
3,ネジを確認(バーを留めるネジが緩んでいる場合があります)
4,チョーク確認。
5,スイッチ確認。
そして、起動です。今回はこの起動の際にスターターロープを引く方向が真っ直ぐでなかった方もありましたので(摩擦で切れてしまいます)




全ての参加者に自分のチェンソーを起動させてもらって、用意した丸太を3cm幅でカットする、姿勢、エンジン音、カットの仕方などを確認します。


ここで、メンバーで確認できたことは、チェンソーに爪が付いているものは、この爪を使ってカットするとより楽に出来るという意見が出ていました。
こんな感じでしょうか。
この作業を、お互いに見ながらする事で、不断は気付かない事も気付かされる点も多かったように思います。「チェンソーの起動、カット」はこれで終了し、次は、先ほどカットした切りくずを見ながら、切れないチェンソーはどこが良くないのか、「つまりチェンソーの刃に問題がある」場合がほとんどですから、今度は「チェンソーの刃を研ぐ」勉強を開始です。
これまでにチェンソーの刃研ぎ勉強会は、何度かやっていますから、そのたび事にお互いの良いものを取り入れて、道具や研ぎ方はますます進化しています。





これはスチールの刃を研ぐ際に、チェンソーの刃に乗せるガイド部品で、正確に簡単に角度を決められると言うことで評判になっていました。

皆さん真剣にやっています。

午前中10時から始めた勉強会は、またたく間に12時を過ぎて、昼食になりました。食事はこの小学校跡を利用して林田夫婦がオーガニックレストランを始めたと言うことで、皆さんここで食事をすることになりました。

午後は、「この季節になってほぼチェンソーを使い終えたと想定して、チェンソーの仕舞い方、保管の仕方」を勉強です。
1,チェンソーのガイドバーと刃を外して、ガイドバーの清掃をします。
この動画は、長い間ガイドバーをあたっていない方がいましたので、これを平やスリで丁寧に左右に出来たバリを取り払っています。このほか、先端の回転する箇所には、グリース。 溝は細いものでゴミを丁寧に取り払っておきます。根元のオイル口の清掃も大事です。





次は、空気を取り入れる「エアーフィルター」の清掃です。この日は、パーツスプレーを使って清掃できるものは、これで細かいゴミを吹き飛ばしてきれいにしました、一部のフィルターではこれが出来ないものもありますので、この場合にはエアーでする場合もあります。
最後の残ったのは、燃料タンクとチェンーオイルタンクの清掃です。下の写真がオイルをすべてタンクから出しているところで、

紙コップに入れてみると中にゴミが入いっているのがわかります。これをコーヒの濾過紙にかければ元通りにきれいな油になります。

写真ではありませんが、この後すべて出しきったタンクから、オイルフィルターを取り出して(取り出せないものも機種によってはあります)灯油やガソリンで綺麗に洗ったり、パーツスプレーでゴミを吹き飛ばします。また、タンク内に残ったオイルもタンクを逆さまにしてパーツスプレーで洗い流して終了です。
次は、燃料タンクです。ここにもフィルターが中に入っていて、これを取り出してゴムから外して、ガソリンやパーツスプレーで清掃します。また、タンク内もオイルタンクと同様に清掃して終了です。
この後、最後に残った最も大事な作業があります。それは、タンクとエンジンのホースに残っている燃料を使いきって仕舞わないと、この燃料が風化してキャブレターが傷んでしまいます。
通常通りにエンジンを掛けて、止まるまでそのままにしておき、止まったらこれで秋まで乾燥した、日当たりの少ない場所に保管します。
皆さんお疲れ様でした。研ぎ澄まされたチェンソーを持ってまた秋に集まりましょう。

動画は、ここをクリック
Posted by 大分エコクラブ at
10:27
│Comments(0)
2014年04月14日
スプレー式のグリース
昨日の勉強会で、グリースの話題が出ましたが、私が使っているスプレー式のグリースを掲載します。
左右のスプレーは一般的なグリースで、右から2番目のスプレーが、チェンソーなどで、高温にも強いグリースです。

そして、左から2番目の物が、キャブレターの中を清掃するスプレーです。これは、チェンソーのキャブレターを開放して、逆さまにしこのスプレーを吹きかけて中に入り込んだゴミなどを落とします。
昨日、参加者にプレゼントしましたパーツスプレーは、エアーフィルターや、機械部分についた汚れを落とすだけで、潤滑油にはなりませんので、注意してください。あくまでも綺麗にするだけです。

これは、スプロケットノーズバー(チェンソーの先端部分の歯車)に注油するためのグリースです。

ここは、回転で熱を持つために、その熱に強いオイルでないといけない様な気がします。メリーで購入。
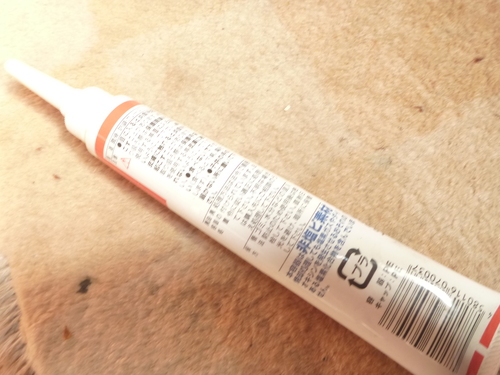
右から2番目のスプレーにも「モリブデン」と書いていますが、このモリブデンが熱に強いのでしょう。
左右のスプレーは一般的なグリースで、右から2番目のスプレーが、チェンソーなどで、高温にも強いグリースです。

そして、左から2番目の物が、キャブレターの中を清掃するスプレーです。これは、チェンソーのキャブレターを開放して、逆さまにしこのスプレーを吹きかけて中に入り込んだゴミなどを落とします。
昨日、参加者にプレゼントしましたパーツスプレーは、エアーフィルターや、機械部分についた汚れを落とすだけで、潤滑油にはなりませんので、注意してください。あくまでも綺麗にするだけです。

これは、スプロケットノーズバー(チェンソーの先端部分の歯車)に注油するためのグリースです。

ここは、回転で熱を持つために、その熱に強いオイルでないといけない様な気がします。メリーで購入。
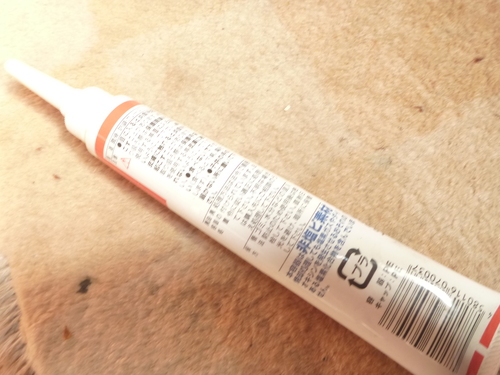
右から2番目のスプレーにも「モリブデン」と書いていますが、このモリブデンが熱に強いのでしょう。
Posted by 大分エコクラブ at
15:03
│Comments(0)
2013年04月05日
チェーンソー燃料の混合オイルを作る(動画)
今週の日曜日に作業するために、チェーンソーの燃料と専用のオイルを混ぜる所を動画にしています。最初始めた頃は、大して神経を使わずに混ぜていましたが、良いチェーンソーを買うとさすがに神経を使うようになりました。要点は、
1,50:1の比率を見てガソリンとオイルを入れる。1度に作るのは、2〜3L程度にする。
2,オイルはハスク用、スチール用、マキタ用の1Lで1000円程度を購入しよう
3,混合したら、すぐに専用の燃料タンクに入れる。ポリの物質がガソリンで溶けて起こらなかったことがあります。
下の動画は、作った混合燃料をチェーンソー本体に入れてみました。
この場合にも、
1,入れる場所は、平地の安定したところで入れる。火気は絶対近くに無いところで
2,キャップは、ガソリンとチェーンオイルを間違えないように。間違えたらすぐにガソリンですすぐ。
3,入れたらしかりと締める(以前こぼしながら切っていたことあり)
4,使わない時期が長い時は全て出して、使い切ること
などを注意しましょう。
Posted by 大分エコクラブ at
16:59
│Comments(0)



